〜出演作品から、20本の映画をピックアップ!〜

洞口依子さんの出演作品から、20本の映画をピックアップして新たに試考してみます。
ですが、じつはまだ、なにを取り上げるかは細かく決めていません。
おまけに、2本、映画ではないものも入る予定。
のうえ、6本は1シリーズとして取り扱う予定。
(出演作解説のコーナーもあわせてご笑覧くださいませ)
〜出演作品から、20本の映画をピックアップ!〜
![]()

洞口依子さんの出演作品から、20本の映画をピックアップして新たに試考してみます。
ですが、じつはまだ、なにを取り上げるかは細かく決めていません。
おまけに、2本、映画ではないものも入る予定。
のうえ、6本は1シリーズとして取り扱う予定。
(出演作解説のコーナーもあわせてご笑覧くださいませ)
|
|
|
|
|
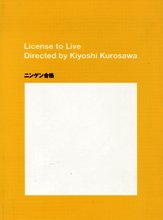 1999年1月23日封切 製作 大映 配給 松竹 109分 「いきなりシーンが変わって、誰かがキャバレーに行けば、そこでは舞台があって必ず歌手が歌っていたわけですね」 黒沢清監督のこのコメントは、金井美恵子氏との対談に載っていたもの。 歌は映画の娯楽的要素の一つなのでどんどんあっていい、たとえば昔の歌謡映画には、という流れでの発言です。 『リュミエール』1985年冬号、公開されたばかりだった『ドレミファ娘の血は騒ぐ』をめぐっての対談でした。 しかしながら洞口依子ファンにとって、この言葉はどうしても『ニンゲン合格』での彼女と結びつきます。 交通事故で中学生の時から意識不明で眠り続けていた吉井豊が、十年後に目覚める。 久しぶりに帰った我が家は、家族が離散したあと。 中学時代の友人は、携帯電話などという見慣れないツールを使って会話している。 昔、家族で飼っていたように、小さな馬のいる小さな牧場を作ろうとする豊。 筋書だけ取り出してみれば、この『ニンゲン合格』には、家族や家庭、現在を生きるということなど、 普遍的な共感を喚びそうな要素がいくつもあります。 しかしそうは易々と卸すはずがないのが黒沢映画のクセのあるところであり、クセになってしまうところ。 洞口依子さんが演じるのは歌手志望の女の子、ミキ。 ひょんなことから、なんとなく彼女と知り合った豊は彼女の歌うクラブを訪れ、 先に黒沢監督の言葉に引いたような「歌手が歌っている」場面が始まるわけですが、 このミキと豊の関係、距離はおもしろいです。 中学生から急に20代の青年にタイムスリップしたような男の物語ですから、性と恋愛の話を避けると、仮にお伽話にしても弱い。 前者は西島秀俊という俳優の茫洋とした佇まいの利いた省略で通過します。 となると後者には当然このミキが当て嵌まりそうなものなのだけど。 知り合った二人が土手に腰掛けて言葉をかわすその空気の不思議な淡さ。 ああ、西島x洞口という、映画界でも得難い個性の二人が会話するシーンには、 こんなにフワフワした、微妙にくすぐったいような雰囲気が醸し出されるのかという嬉しさに、画面を見つめる顔も綻ぶ名場面です。 とくにこのシーンの頭で、依子さんの姿がほとんど映っていないので、二人の男女に交差する愁波を感じさせない。 彼女の持っている楽器のケースを指して、「これ、バイオリン?」 「ううん、ウクレレ」と彼女が答えたところで初めてアップで依子さんを映し、ウクレレを爪弾く彼女をとらえるこの呼吸の麗しさ。 この瞬間、『ニンゲン合格』という映画は、「洞口依子がウクレレを弾く姿」の魅力でいっぱいに充たされます。 何度も何度もこの部分を見返してみて、大袈裟に思われるかもしれないけれど、ここには映画の自由とマジックの輝きと、 それを実現する彼女のシャーマン的な力を感じます。 「わたし、歌手になるの。ニューヨークで」ミキの「歌手」という言葉にも「ニューヨーク」という言葉にも、 豊が否応なしに向き合わされている現実での選択の臭いはなく、この娘はちょっと現実から乖離しすぎなんじゃないかとさえ思わせるほど、 そのセリフを言う依子さんには地に足が着かない危うさがあって、それが痛々しさではなく、 くすぐったいような薄い甘さを味あわせるのが、この作品での彼女の魅力ですね。 そして彼女が歌う場面。 |
『芸術家の食卓』と『陰翳礼賛』 洞口依子という女優を動物で何に譬えられるというと、やはり猫ということになるでしょうし、 私もそんなような事をネタに記事を書いたことがあります。 しかし、本当に彼女を猫にしてしまった演出家は、後にも先にもこの人以外にいないでしょう。 宮田吉雄。 TBSで久世光彦氏のもと、『寺内貫太郎一家』や『ムー一族』など、タイトルを聞いただけで、 一家に一台しかなかったテレビを家族で見ていたあの水曜の夜がよみがえるような番組の演出陣に参加、 退社後には久世さんが設立したKANOXへ移って、2004年10月に66歳で亡くなられた演出家/プロデューサー。 と、訳知り顔で書いていますが、じつは私も宮田さんについては、これに加えてほんの少しの逸話を耳にはさんだ程度です。 最近出版された小林竜雄さんの『久世光彦 vs 向田邦子』(朝日新書)にこの不世出の鬼才についての記述があり、そこには、 久世は後輩の宮田を「狂気の教養人」で「桁外れの奇人」と大袈裟に賞賛し、その異才ぶりを愛していた (上掲書 p.133より) と、簡潔で興味をかき立たてられる一文が織り込まれています。 私が宮田さんに惹かれた端緒も、これに似た言葉のポートレイトからでした。 洞口依子さんは『芸術家の食卓』『陰翳礼讃』『埋葬された愛』という3作の宮田作品に出演されています。 また、1987年、篠田正浩監督が進行役を務められたTBSの旅/情報番組『日本が知りたい』では、 依子さんと鈴木ヒロミツさんが小豆島を案内した回の演出が宮田さんで、これを知ったときは、本当に吃驚しました。 それはリメイク版『二十四の瞳』の公開にあわせたものだったのですが、島の観光スポットを紹介するところどころに、 情報番組では普通見られないような、なんとも不可思議な趣が漂うものだったのです。 ヒロミツさんが一人で道を歩いている姿からカメラが引くと、依子さんがぼんやりと腰かけているのが映っていたりする。 2人は同じ番組の同じ回のレポーターなのだけど、お互いの存在には気づかない。 だからナンだと言われると返答に困るのですが、そこに洞口依子がいることが醸しだす異化効果は無視できないもので、 どんなに風光明媚な観光スポットよりもその場所が頭に焼き付いて離れなくなる。 この種の番組の趣旨に沿ったものなのかどうか、そのへんは怪しく思えてくるんですが、 私のようなヒネた視聴者は、「なんか面白いんじゃないか?この土地」なんて、なんとも妙な具合に好奇心をそそられたりする。 それが宮田吉雄さんの演出だったのでした。 『芸術家の食卓』と『陰翳礼賛』は、1989年と1990年、まだ手探りの状況だったと伝え聞く「HDTV」(ハイヴィジョン)で TBSが製作した作品です。 それぞれ24分と52分の短いもの。 しかしながら、観ると圧倒されます。 どちらも生活スタイルの細部に徹底してこだわった視点で、奔放にして才気旱魃たるヴィジョンが これ以上ないくらいに凝縮した濃密さで描かれます。 写真家の西川治氏が自分の求める「食」を追求する姿をセミ・ドキュメンタリーふうに追った『芸術家の食卓』、 谷崎をベースにした筋立てに、日本家屋に潜む死とエロティシズムの陰翳をデュ・プレのエルガーが匂い立たせる『陰翳礼賛』、 どちらにも、洞口依子さんの魅力が輝いて在ります。 それが作品に奇妙なエレガンスをもたらしています。 そこに洞口依子が映る、それがどういうことなのか、宮田さんは知り抜いていたのだろうし、 そのうえでなお予想できないものがあったからこそ、こんなイメージの奔流のなかに彼女を放り込んだのだと想像しています。 まずめったに観る機会のない2作ですが、TBSメディア総合研究所のご厚意により、「洞口依子映画祭」で劇場(!)公開 させていただくことになりました。 貴重という言葉だけでは言い尽くせない価値のある上映です。 もっと宮田吉雄を! 『芸術家の食卓』(1989 TBS) プロデューサー 前川英樹 演出 宮田吉雄 撮影 安藤紘平 浜田泰生 美術 宮沢利昭 出演 西川治 洞口依子 24分 『陰翳礼賛』(1990 TBS) プロデューサー 前川英樹 演出 宮田吉雄 脚本 原田菜緒子 撮影 浜田泰生 美術 飯田稔 原作 谷崎潤一郎 出演 長谷川初範 眞行寺君枝 洞口依子 不破万作 石堂淑朗 成田繁範 52分 (お名前に誤表記がある場合は、恐れ入りますが、yorikofans@yahoo.co.jpまでご連絡ください。) |
『ドレミファ娘の血は騒ぐ』  1985年11月8日封切 製作 EPIC・ソニー ディレクターズ・カンパニー 80分 洞口依子登場。 洞口依子エクスペリエンス。 『ドレミファ娘の血は騒ぐ』について、彼女のファンとして何かを言おうとすると、 結局はそのような文句でしか始まらず、そのような文句でしか終われません。 初めてこの映画のポスターを見たとき、 見たこともない女の子が映画のポスターにデカデカと描かれていて、 『家族ゲーム』や『細雪』や『お葬式』で有名な人が映っていて(高校生の私にとって、これが実感できる限度でありました)、 ワケのわからない、だけど何度も口に出して読みたくなるようなタイトルが、真っ赤に飾られて躍っていて、 挑発されるような、見限られるような、けれど底意の何かと共振しあえるような、 いったいこれはなんなんだと心が騒ぐのを抑えきれませんでした。 ドレミファ娘の血は騒ぐ、ドレミファ娘の血は騒ぐ・・・この子が「ドレミファ娘」とやらなのか? なんだ、「ドレミファムスメノチワサワグ」って? 自分に関係があるような、端っからまったくないような、だけど文字の並びを見ているだけで、やけに痛快に思えてくる。 だから手を伸ばしてみたいのだけど、取り付く島もないというか、やがてそんな想像はいつのまにかタイトルからこの子へと戻ってしまう。 そして、それとほぼ同じことが、時間を置いてようやく観ることができた映画でも起きたのです。 1984年の5月8日から5月18日までの11日間、1000万円の予算で撮影された映画です。 洞口依子さんはこのデビュー作の現場のことを、「本当に心地良い時間が流れていました」と、 溢れんばかりの思いがとても美しい『ユリイカ』誌(2003年7月 黒沢清特集号)でのインタビューで語っています(p.103)。 しかしこの映画はそこから先、公開までのあいだに多難な道を経ることになります。 当初『女子大生恥ずかしゼミナール』という成人映画として制作されていたこの作品は、 「難解である」「いやらしさが足りない」との会社からの意見により、お蔵入りになる寸前までいきました (本当はもう少し込み入った事情があったようですが、『黒沢清の映画術』新潮社に詳しいのでそちらをぜひ)。 これをディレクターズ・カンパニーと当時の依子さんの事務所が協同で買取り、成人指定を外すために幾シーンかをカット、 短縮された尺を20分の追加撮影により80分に仕上げて完成したのが『ドレミファ娘の血は騒ぐ』です。 前掲書の監督のインタビューによると、改変される前の『女子大生恥ずかしゼミナール』は、本来ポルノとして「真っ当なもの」(p.94) だったそうで、ビデオで追加撮影された箇所がお蔵入りの判断材料となったのではないのは確かです。 などと書いている私も、初見の際には、あのビデオ撮りも当初からの演出だと思いこんでいたのですが。 これは昔からの疑問なのですが、『ドレミファ娘の血は騒ぐ』というタイトルは、いつどの時点で付けられたのでしょう。 現在もピンク映画などでは、DVDリリース時などに劇場公開時と全くちがうタイトルがつけられることはよくありますが、 『ドレミファ娘』の場合は、別の作品として生まれ変わったものに対して新たに名づけられています。 作品を買い戻して一般公開に向けて追加撮影を始めるとなった時点でタイトルを変えたのか、 もしくは追加撮影も終えた時点で、『ドレミファ娘』となったのか。 つまり、あの追加したシーン〜特に最後の戦闘シーンを撮るとき、スタッフとキャストの頭には、すでにそのタイトルがあったのか。 それとも出来上がったものを、監督が『ドレミファ娘の血は騒ぐ』と新しく命名したのか。 なぜこんなことに興味があるかというと、シロウト考えかもしれませんが、 『ドレミファ娘の血は騒ぐ』というタイトルは、言葉は、非常に刺激的なものだと思うのです。 知的に屈折したユーモアのセンスが感じられて、なおかつ掴みどころがない。 はぐらかされる愉しみが味わえる。 曖昧でありながら挑戦的な匂いもします。 挫折と苦渋を経てようやく公開されるとなった作品にシーンを撮り足すとき、こんな秀逸なタイトルが冠せられていると、 スタッフ、キャストのモチベーションは大いに影響されるのではないでしょうか。 この作品のこととなると、私もついつい元の『女子大生恥ずかしゼミナール』に思いを馳せてしまいがちだったのですが、 現在はむしろ、作品が生まれ変わってゆく段階での関係者の気持ちがどうだったのか、私はそのことに興味があります。 けれど、この映画がどんな背景を秘めたものであったにせよ、洞口依子さんの存在感は全編を通じてピタリと焦点が揺るぎません。 『女子大生恥ずかしゼミナール』として撮られたあの「とうとう来ました、吉岡さん」のオープニングでの彼女と、 追加撮影されたあのエンディング、白い衣装(依子さんの自前)で機関銃を片手に「ブラームスの子守歌」歌う彼女のどちらにも、 または微笑みにもふくれっ面にも、一糸まとわぬ裸にもピンクのセーターにも、スキップする姿にも気絶して自転車で運ばれる姿にも、 あらゆる桎梏や纏足に気だるくも抵抗する精神が息づいていて、それが可愛さとなって輝き、エロティックにきらめき、 つかまえたと思うとすり抜けていってしまうその光は、鮮やかで痛快です。 この映画そのものです。 この映画を観るたびに、何度でも洞口依子登場を体験できます。 その都度、観る人にとって、彼女は新しく登場するのです。 洞口依子登場。 洞口依子エクスペリエンス。 (この作品に関する資料などは、「ドレミファ娘の血は騒ぐ」の資料本をお読みください。) プロデューサー 荒井勝則 山本文夫 監督 黒沢清 脚本 黒沢清 万田邦敏 助監督 万田邦敏 音楽 東京タワーズ 沢口晴美 出演 洞口依子 伊丹十三 加藤賢崇 麻生うさぎ 暉峻創三 岸野萌圓 勝野宏 久保田祥子 渡辺純子 新田努 今野詩織 神藤光裕 立原由美 山路みき 可知亮 摘木満江 小中和哉 林珠実 篠崎誠 角田亮 高橋健司 岩岡禎尚 清水俊行 笠原幸一 浅野秀二 |
『ミカドロイド』 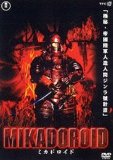 1991年11月8日ビデオ発売 製作 東宝 円谷映像 東北新社 配給 東宝 76分 80年代の後半から90年代、ビデオ店の棚を賑わせていたのが、劇場公開を前提としない「オリジナルビデオ」(OV)のタイトルです。 まず東映の「Vシネマ」(その後、このカテゴリーの代名詞的名称ともなった)が成功し、これを追うように各社がマーケットに参入。 東宝が「東宝シネパック」と銘打ってコケラ落としに制作されたのが、この『ミカドロイド』であります。 監督は、日本の特殊メーキャップの第一人者、原口智生氏。 この作品での洞口依子さんについては、当サイトで原口監督にインタビューをさせていただいたことがあります(こちら)。 また、2002年発売のDVDには原口監督と樋口真嗣特技監督との対談がオーディオコメンタリーで収録されており、 この2つを基に見ていくと、いろいろと興味深いことがわかります。 もともとこの作品は『ミカドゾンビ』というホラー作品として発案されたものであったのですが、 89年の「埼玉幼女誘拐殺人事件」の余波として起こったホラー/スプラッタ自粛のあおりを受けた結果、現行のアクションものへと変更されたそうです。 『ドレミファ娘の血は騒ぐ』を見ていた原口監督が洞口依子さんの出演を熱望されて、旧知の黒沢清監督(本作にもカメオ出演)を通じてそれが実現。 黒沢監督は、この後に『勝手にしやがれ!!』シリーズほかOVの傑作を撮り、同シリーズでは依子さんが出色のキャラクター羽田由美子を演じ続けました。 私が『ミカドロイド』のことを知ったのは、91年の『キネマ旬報』10月下旬号に掲載された依子さんのインタビューで、 ネットがなかった当時には、雑誌が映画全般についての貴重な情報源でしたし、OVについての情報となるとじつに乏しいかぎりでした。 ところが、この『洞口日和』を始めて、何人かのかたとやり取りをするうち、『ミカドロイド』が自分が思った以上に「語られている」作品であると気づいたのです。 一人は、ミリタリーマニアのかたでした。 『ミカドロイド』は旧日本軍が極秘 裡に開発しながら中止となった人造人間「ジンラ號」が、バブル末期の渋谷のディスコ地下で甦り、 駐車場で殺戮を繰り返したのち、閉じ込められた1組の男女を追い回す、というストーリーです。 その方面に疎い私には到底わからないような、ミリタリー系のディテイルを、私はそのかたから教えていただきました。 あのジンラ號のズングリムックリした外見も、かつて実在した空挺部隊の外装に通ずるものがある(youtubeで確認しました)とか、 思いがけないところで知りうることができました。 次に別の銃器マニアのかた。 このかたには、ジンラ號の装着する武器類(日本刀も含む)が、史実に則りながら独創性の高いもので、かつ低予算で造るには難易度の高いものある、 と教えていただきました。 また、リリース時に銃器/ミリタリーの専門同人誌でこの作品を取材した記事があったなんてことも、私はまったく知りませんでした。 それから、特撮マニアのかた。 CGなどのポストプロダクションに頼らずに、いかにアイデアとセンスと技術で、(これまた)低予算で敢行された現場であるか、 あまりにお詳しいのでスタッフのかたかと思いこみましたが、そうではないようです。 マーちゃんという役者さんが、ミニラのスーツアクターのかただと教えていただいたのも、原口さんの特殊メーキャップの実例を教えていただいたのもこのかたです。 そして、黒沢清監督マニアのかた。 外国のかたでして、「クロサワが出てるんだよ!」とレクチャーされましたが、さすがにそれは知っていました(笑) でも、うれしかったです。 この作品には、その道のマニアたちが思わず「語りたくなる」何かがあるように思えるのです。 潜在的にあるフリークっぽさを刺激してやまないというか、日常をついつい逸脱して何事かにのめりこんでしまう人間には他人事とは思えないところがある。 他人の鏡のどこかに写ってる自分を見つけてしまう。 その鏡をさらにぐっと覗き込んでしまう。 自分と同じではないんだけど、自分もこの人の鏡に写っちゃうんだと不思議に納得させる。 「スクリームクイーン」(SQ)という言葉がありまして、たしか戦前の『キングコング』のフェイ・レイくらいが始まりなのかな、 ホラー映画などで悲鳴をあげる演技で作品を輝かせている女優のことですが、『ミカドロイド』の依子さんもその殿堂入りです。 ミカドロイドに遭遇するまでの彼女は、ディスコで不機嫌な表情を浮かべて座っています。 バブル期の街の空虚な盛り上がりの中で倦怠感を漂わせる女。 それがアンニュイに流しっぱなしではなく、反抗的な肝の太さが窺えるのが彼女ならでは。 どこにも流れ着かない感情があって、それが彼女を周囲から際立たせるし、自身をいらだたせもする。 その彼女が、ミカドロイドに追われることで緊迫した状況の中に放り込まれる。 地下壕に足を踏み入れた途端に、スーツの色も白から灰色に変わる(いちばんショッキングな場面かもしれない)。 一緒に逃げる男もさして頼りにならない。 何かを仕掛けて逆襲に転じれそうな場所がいくつかあるけど、そこも逃げて通り過ぎる。 何度か登場する彼女の顔のアップが印象に残ります。 目を見開いてジンラ號の姿におびえる表情ですが、これが直反応の恐怖というより、どこか霞みがかったような曖昧さを感じさせる視線です。 すぐ足元まで恐怖が迫ってきているときに、まだどこか茫然と心ここにあらず。 そんな洞口依子さんの放心エッセンスがここに光っていると思います。 彼女のこういう魅力は、できれば映画館のスクリーンで味わってみたい。 彼女が最後の最後になってようやく(しかしながら飽くまで偶然に)反撃に転じた直後、 爆風の後尾がゆっくりとゆっくりと吹きつけてくるなかでジンラ號を見つめるその目。 勝利の喜びや逃げ切った安堵とは別の、もっとセクシュアルな高揚と虚脱に似た解放感をも伝えるこの表情が素晴らしいと思います。 さまざまなフリークたちの創る思いが、見る思いが、渦巻いて惹きつける、マニア受難の89年から始まった「地獄の逃避行」’91です。 おそらく依子さん自身が、この濃厚に思い入れの溢れる「場」とごく自然に反応したのではないでしょうか。 それぞれが、「『ミカドロイド』は〜の映画です!」と言ってしまっていいでしょう。 では、私も。 『ミカドロイド』は、洞口依子がおびえ、逃げ、泣き叫ぶ映画です! (勁文社のムック『幻想世界の美少女たち -円谷映像作品集』には、見開き2ページで『ミカドロイド』の洞口依子さんを論じた記事があります。) 監督・原案:原口智生 脚本:原口智生、武上純希 特技監督:樋口真嗣 音楽:川井憲次 ガンエフェクト:BIGSHOT 監修:実相寺昭雄 出演 洞口依子 吉田友紀 渥美博 マーちゃん 伊武雅刀 速見健二 毒蝮三太夫 光益公映 黒沢清 林海象 手塚真 破李拳竜(ジンラ號) |
|
『君は裸足の神を見たか』 出演 |